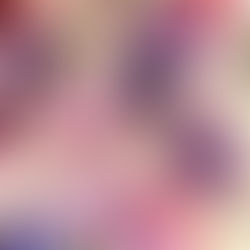人・物・情報が国境を越え行き交うこのグローバルな時代とは逆流するように、独自の文化・慣習・血を途絶えることなく紡いできた少数民族と呼ばれる人たちが、ここタイにもいる。
カレン族は何世紀も前からタイとミャンマーらへんに住んでいる少数民族で、そこからさらに複数の異なる部族に分かれている。正確な統計は見つからなかったけど、だいたい50万人ぐらいのカレン族が今もいるそうだ。主にタイ北部の山岳地帯に住み、音楽、踊り、衣装、言語など、農耕民族として衣食住にまつわる独自の生活文化を脈々と紡いできた。数千年と変わらぬまま、山岳地帯で山や森と生活することを続けてきている。
しかしながら、タイの少数民族は社会的に立場が弱い。例えば、彼らは独自の言葉を持っているが、市民権を認めてもらえるためには、タイ語を習得し、出生証明書などの書類を揃えなければいけない。現実問題は色々とあるようだ。パイナパイタホームでは彼らの伝統技術と芸術感覚を現代社会に伝えるために、カレン族の女性による「カレン族の伝統染色と裁縫の会」が定期的に開催されている。
近年クラフトという言葉・概念が脚光を浴び、マスプロダクトとは対極にある、人の手と目と感覚で作り上げる工芸の尊さを見つめ直す風潮が勢いを増している。日本の伝統工芸というと、特定の技術の継承とその革新に重点を置き、調度品として発展してきたが、今日では高級品のため一般人には少々縁遠いものとなっている。他方、今回の”クラフト”は、どちらかというと民芸に近い。工芸と民芸。一見似ているようだけど、よく考えると性質は違うような気がする。工芸は巧みの技を駆使した一級品というイメージだが、民芸はもっと私的で、自分たちが使うことを目的に作られた、日用品や祭事などを含む民族的独創性を表現する目的に存在価値が見出されている。
民族衣装、衣服もその一つ。染め上げた布一枚、刺繍の柄一つでどこのだれかを判別することができるように、他の地域と差別化をし、自分たちの民族意識を主張してきた。見た目が9割という説が本当かどうか知らないけど、オリンピックの国ごとのユニフォームのように、各部族は着るものにこそ意味を持たせ、プライドを築き上げてきたのだと思う。外見で多くの情報を判別していたのは間違いない。

色鮮やかな刺繍が入ったプルオーバーのシャツを着た、私と同い年ぐらい(30代前半)ぐらいの女性が今回の先生だ。彼女はパーイから2時間ほど離れた集落で生まれ育ち、これまで伝統的な生活様式や芸術文化などを一通り学んできた。次世代のカレン族の一人として、またさらにその次の世代を育てる子の母として、少数民族の血だけでなく、生活技術を受け継いでいる。今日1日、彼女から染色と刺繍を教わる。
染料は3種類の材料を用意してくれた。
藍、グズベリー、泥。外にある焚き火台には大きな鍋が置かれ、剪定したなにかの木の枝が燃えている。藍には錆びた鉄、グズベリーには石灰、泥にはミョウバン。それぞれの材料に隣には、色止めのための材料が皿に入っている。まずは染める前の布を湯が沸いた鍋に入れ、すこし煮込み、色を入りやすくする。

ちなみにグズベリーは日本語ではセイヨウスグリというらしく、一応日本でも誰かが栽培してるらしい。お湯を張った鍋にグズベリーをいれ、火にかける。煮立つまでの間、彼女の集落で栽培した藍の生葉を包丁で細かく刻み、石臼の中で餅をつくように潰していく。
ドスドス ジュッジュ
染色の工程には様々な音や温度、匂いや感触があり五感がフル稼働して面白い。
石臼で潰した藍の葉っぱをタライにいれ、さらに手で力強く揉むことで繊維に傷をつけ、色素を出していく。青色と灰色を混ぜたような紺色の液体ができた。そこにゴムで縛って模様をつけた布を入れて揉み、しばらく漬け込んでおく。そうこうしているうちにグズベリーが入った鍋は湯がたち、濃い茶色の液体がブクブクと泡を吹いてきたので、こちらにも染める布を投入。ちなみに藍と泥は煮立てる必要がないみたいなので、常温の染液にそのまま直接布を入れた。
太陽はあっという間にてっぺんに上り、ランチの時間になった。この日もケロちゃんがたくさんご馳走を作ってくれた。黒米、ココナッツミルクのスープ、豆腐の炒め物、オムレツ、魚と野菜の炒め物、、、。テーブルの端から端まで見た目だけでは味の想像がつかい美味しそうなものが並んでいる。ワークショップに参加している、ドイツ人の子とイスラエル人の子も一緒に、みんなでテーブルを囲んだ。

午後は、染液につけた布を洗って干した。藍は紺色、グズベリーは灰色��、泥はオレンジに染め上がった。染液から取り出し、水で洗い、輪ゴムを取って、布を広げる。それまでどんな仕上がりになっているかわからない。この布を広げる瞬間が一番の醍醐味だった。持っていた白いTシャツやエコバッグ、小物入れなど見渡す限り染めれそうなものは全部入れた。どれ自然みのある鮮やかな色に仕上がり、模様も綺麗に出ていて大満足の出来だった。
染め物のワークショップは世界各地で開催されているだろうし、同じ染料もいろいろな場所で使われていると思う。だけど、どこで誰から教わるか、と合間に何を食べるかで同じ内容も全く違う体験になるんだと思った。染め物が終わったら、次はケロちゃんのお洋服屋さんに場所を移し、刺繍の会が始まった。私はカレン族の花の刺繍柄の縫い方を2種類教えてもらい、お気に入りの作務衣の上着に縫うことにした。
先生は作業台の上で上着に定規を当て、線を引いて印をつけてくれた。そして、一目一目針の行き先をゆっくりと見せながらお手本を一個作ってくれた。黙々と針と糸を見つめていたら、あっという間に2時間が経ち、日も傾きかけていた。残りはまた夕ご飯の後やることにして、記念撮影をしてその場で会はお開きとなった。
夕食後、ベッドの上で続きを縫っていたら、あっという間に日を跨いでしまい、あわてて電気を消した。目を瞑ってもしばらくは頭の中で針と糸の動作が続いていて、このまま刺繍のアクセルを踏み続けようと心に決め込んでいたら、スーッっと眠りについてた。
今回の一番の学びは、着るものを作ることは、単に生活のためではなく、民族的アイデンティティの表現活動だということ。誰かが着ているものと同じものを着るなんて、少しもも面白くない。大量生産されたものを身にまとい、自分らしさを見失うくらいなら、私はどこにも売ってないものを自分の手で作り、身に纏うことで、オリジナルを模索していきたい。あと、ここ数年ワークショップを企画側に立ちっぱなしで、自分が受ける側になることを忘れていた。だから、久しぶりにこうして丸一日、人から直接学ぶ時間を過ごすことができてとてもよかった。

パイナパイタでは定期的にワークショップが開催されているから、タイに行ったら是非、参加してほしいと思う。