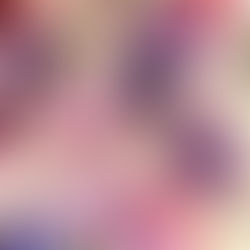ウィアンタイ公園。街の中心にあるこの広場は週末になると多くの人で賑わう。地元の人、移住者、旅行者、大人から子どもまで人がたくさんだ。コロナ禍の中、ケロちゃん含め地元の有志で発起したサタデーマーケットは、今ではバイクを止める場所が見つからないほど多くの人が集い、公園はいろいろなお店がびっしりとひしめき合っている。その中には、子どもによるレモンジュース屋さんまである。
地元警察に了解をとり、このマーケットでは就労ビザだとかビジネスのための証明書だとか、面倒な手続きのことは気にせず、繋がりがある人であれば、誰でもお店を出しても良いそうだ。出店料は特にない。マーケットは一応10時からだけど、みんな好きな時間に来て、好きな時間に店をしまっている。カオソーイ屋、お菓子屋、アクセサリー屋など、自分で手作りしたものを並べている人が多かった。他、道端から拾い上げたものなのか、骨董品と呼べるものなのか、それとも家にあったいらなくなったものなのか、どれも当てはまるような判別のつかない、まさに雑貨屋と名にふさわしい店もあった。

全体の雰囲気として、おしゃれだとかそういう誇示的でマーケティング臭い様子はどこにも見当たらず、人種すらもランダムでゆるい。そもそもみんな売れるものをつくることを目的にしていなくて、それぞれ心底好きなもの出品していて、文化祭のような青春の頃の純粋さを大人の世界にそっくりそのまま写した、理想の市場がそこにはあった。
ケロちゃんももちろん出店者。朝、彼女は毎回大きな荷物で行くのが面倒だといい、バイクの前についている籠を棚にして、その上で商品を売るという算段を教えてくれた。なので出店用と何かあった時の移動を考え、2台のバイクで行くことにした。ケロちゃんのバイクは通りの市口付近、カオソーイ屋と古着屋の間に設置した。バイクの座面は布で隠し、前のカゴに板を置き、バナナの皮でデコレーションをして、ものの数分でお店が完成した。今日の商品は自家製コンブチャとキノコが入ったの餅米をバナナの葉っぱで蒸したもの。日本のチマキのようなもの。

コンブチャを並べ、チマキを並べようと思ったが、どこにもない。小さな荷物できたから探す場所はバイクの中にしか無く、家に忘れたんだとすぐに目星がついた。そうだ、バンちゃんに連絡して、もう一台家にあるバイクで届けてもらおうということになり、バンちゃんにヘルプを要請した。すぐにバンちゃんから返信がきたが、朗報ではなく、悲報だった。家中どこを探してもバ�イクの鍵がないそうだ。完全に焦るケロちゃん。
ケロちゃんの中にある、なんらかのボルテージが最高潮に達したその時だった。
「ニャーーー!」ケロちゃんの素性があらわとなり、一匹の猫の叫び声が周囲に鳴り響いた。自分の部屋でくつろいでいるかのように、バイクの鍵はケロちゃんのカバンの中で横たわっていた。
「ケロちゃん、大丈夫、わたしが行くよ。」と言い、バイクで風を切る爽快さに至高の開放感を毎度感じている私には、家まで帰るぐらい朝飯前だった。すぐに来た道を戻り、パイナパイタにつくと、バンちゃんがバットに入ったチマキを持ってきてくれたが、スチールのバッドが大きすぎて、座面の下にも足元にも収まらず、困ってしまった。バンちゃんにどうしたらいいかな?と聞いたら、足で挟めば大丈夫といいながら、仕事へ戻ってしまった。
一人になり、もう一度安定する場所を探したが、ダメだった。こんなに美味しそうなもの、なにがなんでも絶対に落としたくないという強い気持ちでチマキを安定させるしか方法はなかった。紐の上の歩くかのような慎重さで、ハンドルを握りしめ運転に全集中した。無事に会場へ辿り着いたとき、事は一件落着し、異国の地でサーカス団の一員として認められたような気分をチマキと一緒に噛み締めた。お礼にもらって食べたチマキは、森の肉のような繊維質のキノコが解き放つ風味とバナナの葉の香りが餅米にぎっしりと詰まっていて、とても美味しかった。キノコに魔法はかかっていなくても、ケロちゃんの料理そのものが魔法のようだと思った。
コンブチャと葉っぱ蒸しは大人気で、2時間たらずで全て売り切れてしまった。周りを見渡すと店の周り、木の周り、至る所に人の輪ができていて、みんなずっとぺちゃくちゃ喋っている。買い物はひとつのきっかけにしかすぎず、みんなの一番の目的は人に会いに来ていることが一目瞭然だった。毎週土曜になるとゆっくり会える人たちがいるようだ。
そんなスローでピースな昼下がりを満喫できるこのマーケットは、地元の人にちゃんと愛されていて、街の中でとても大切な役割を担っていた。
また、ここで再会できるのは人だけにとどまらず、ケロ�ちゃんが以前保護していた犬がこの近くで飼われていて、その子と戯れることができるのもマーケットに出る楽しみの一つのようだった。
遥か昔、古代文明より人々の生活の中核を担うマーケット(市場)。本来、誰でも売ったり買ったりできる。ネットショッピングでは手に入らない、人と人、人と物の有機的な繋がりを感じることができる。作り手が買い手へと直接渡すことは、つい最近まで当たり前の光景だったことを思い出した。建物一つにAからZまでなんでも揃う大型モール、ボタン一つで欲しいものが買えるネットショッピングが、いつしか買い物の大半を占めるようになってしまった。この味気ない消費行為が当たり前になると、味気ないと感じることすらなくなってしまうのが寂しいと思った。

人の顔を見て、目の色や表情と一緒に品物を受け取ることができる、個人露店しかないマーケットで買い物をするのは、心から楽しいと感じれる。おばちゃんが子ども用のプールぐらいありそうな大きな鍋に豪快に食材を投げ込み、カオソーイを作っていた。付け加える度にみるみる色が変わっていく濃厚な汁を見つめながら、出来上がるのをじっと待っていた。こうして間近で、それも頭から足まで全身調理の動きを座って眺めることができるのも屋台ならではの醍醐味だった。
ついに出来上がった。すぐに列に並び、順番を待った。出来立てのカオソーイを受け取り、同じくパイナパイタに滞在していたアルチューっぽい挙動不審なノルウェー人の男の子と一緒に食べた。彼はいつもお酒を飲んでいてフラフラしていて、旅の予定を聞いても意味不明で、会話もちぐはぐで、ちょっと心配だったけど、静かめでいいやつだった。
作り始めからずっと見ていたカオソーイ、生まれて初めて食べるカオソーイに相応しい、ローカルならではの絶品だった。
身の回りにどうでもいい適当なものなんてひとつもない。どうでもいい一食もまたひとつもない。
全てのものに人の手が触れていて、それらを含めて私自身の一部なのだから、ただの消費者になることはもうやめて、人の温もりを生で感じられ、そこから何か新しい命が芽吹くようなものを作りたいし、手と口に入れたい。
パーイのローカルマーケット。出店料とかオーガナイズフィーとか場所代とか何もないけど、きっと彼らにとって意味のある形で且つ楽しく続けられ形がこれだったのだろう。人が自由にモノを売り買いし、ジャーの中で酵母菌がしゅわしゅわと弾けるように賑わう理想の市場。街全体が市民の自由という絹の衣に包まれたような安心感に満ちている街の風景を肌で感じ、確かにそこに今いる現実をしっかりと胃袋に収めたのだった。