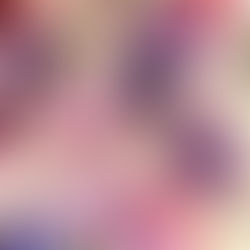パイナパイタの心地良さに名残惜しさを残しつつ、次の目的地へ。
朝6時にむくりと起き上がり、ケロちゃんがお弁当に持たせてくれたカットマンゴーを頬張りながらぼやけた頭に糖分を投入し、眠気を覚ました。急いで荷物をパッキングして、7時にはバイクの後ろに座り、チェンマイの朝の風景を眺めながら空港へ向かった。今日のフライトはチェンマイーバンコクーバンガロールーコインバトーレ。乗り換えの時間が短く、空港に着くたびダッシュしなければならなかった。インドのE−VISAを申請手続きをすべて済ませていたつもりだったが、事前確認を行うのが遅くなってしまった。2日前に確認したけど発行されているはずのビザの書類が見つからず、大使館にメールを送ったが「ない」と言われてしまった。しかし、日本人はインドに着いてから、その場で到着ビザを申請できるので、乗り換え時間内に済ませる作戦に急遽変更した。南インドはバンガロール空港に着き、急いで到着ビザの申請窓口へ向かった。乗り換え時間は1時間半。焦る気持ちで窓口に着くと、おっさんが力の抜けた顔でスマホを凝視しながらソリティアをやっている。まじか。幾秒かの間おいて、やっとこっちに顔を向けてくれた。
申請用紙�を渡され、走り書きで記入した。内容はE−VISAの10分の1程度だったため楽勝だった。窓口へ戻ると、まだソリティアをやっている。一応こちらの状況を把握してもらうため、乗り換え時間が短く急いでいることを説明したが、おじちゃんは捲られてくるトランプの絵札のほうが気になるようだ。申請用紙を渡たすと、スマホと書類を交互に見ながら、しばらくした後、書類を突き返された。「帰国のフライト番号を書け。」と言われたが、そんなの決まってないし、あえて決めない旅がしたくて帰りの切符を買っていない。どうしようかと思ったけど、とりあえず日本からタイへ行く時に乗った飛行機のフライト番号を記入してみることにした。もう一度窓口へ行き、書類を渡すとすぐにOKがでた。何かが書かれていればそれでいいのだろう。そもそも彼にとっては私の書類、ないし帰国予定よりも目の前のソリティアの方が遥かに重要なのだろう。ソリティアとおっさんに対する苛立ちは、目的が達成されると感謝に変わった。
審査ゲートまで行き、更にいくつか質問に答えた後、ビザ費用の4000ルピー(8000円)の支払いを済ませ、ついにスランプを押してくれた。とはいえ1時間近くかかってしまった。ゲートが閉まるまで残り30分。小走りで一旦外に出て、バスで別ターミナルまで移動し、三息だけタバコを吸って、再びエアラインの窓口へ向かった。デスクにつくなり、「荷物を預ける時間はない。とにかく急げ。」と言われ、全力で走った。バンガロール空港はそこそこ大きくて人も多い。手荷物検査でお気に入りのキノコステッカー付きのライターを捨てられたのは惜しかったが、抗議する時間はないと思い諦めた甲斐あって、ギリギリセーフで席についた。
コインバトーレ空港からタクシーに乗り、明日乗るバス停近くのホテルへ向かった。バス、車、バイク、チャリ、歩行者が狭い道に無造作に溢れかえっている。車線はない。道路という一つの巨大な生き物のようだ。1人が転んだら多くの人を巻き込む大事故になりかねないと心配になったけど、これがここの”いつもの光景”だと思ったら、阿吽の呼吸で進む地元民たちに妙な安定感を感じていた。不安定なところで安定している窓の景色を眺めてたら、あっという間にホテルに着いた。ホテルへのチェックインを済まし、Googleマップでなんとなく良さそうな地元料理が食べれるお店をみつけた。朝のマンゴーとバンガロール空港で急いで買ったクリスピークリームの激甘ドーナッツの他、何も食べてない。お腹が空いた。

部屋から一歩外へ出るとそこは異世界だった。交通量の多い道路に店、出店、駐車したバイク、人間がサンドイッチされている。そこに微かに残された人が歩く道を目でなぞりながら一歩一歩進んでいく�。お店に着いて、メニューを見たけどわかんないから、適当に注文した。皿がわりに大きなバナナの皮が目の前に敷かれ、鶏肉と玉ねぎとチリの炒め物とチャパティを持ってきてくれた。その後、チキンカレーとベジカレーを持ってきてくれた。美味しい美味しいと食べていると、さらに3種類もってきてくれ、皿にかけてくれた。どういうシステムなんだろう、いやそもそも型など存在しないのか。美味しそうに食べていれば、次々と持ってきてくれるのか。どれも激辛だったけど、激辛好き故ぜんぶ美味しく平らげた。バナナの皮を捨てて手を洗い、店員とキッチンにお礼を言って店を出た。お腹いっぱいで大満足だ。タイに比べ、インドはスパイスの主張がもっと強い。スパイスも食材の一つのようだ。
帰りは来た道の反対車線を歩いた。前から突進してくるバイクに注意を払いつつも、足元を見てなくちゃいけない。ゴミ、パイプ、木、穴、とにかく地面は障害物だらけ。腹を満たしご機嫌で歩いていると、一本の木の下に便器が置かれていた。最初は「あー便器ね」と難なく通り過ぎたが、「やっぱり、おかしい」と思いすぐに踵を返した。木の下に、もういらなくなって誰かが捨てた便器がある。見るからについ最近置かれたものじゃない、もっとずっと前からここにある風貌をしている。不用になった便器はすっかり道路の一部に溶け込んでいた。
なぜ便器はそこに落ちているのだろう?誰がそこに捨てたのだろう?新しい便器をゲットして古い便器はいらなくなったが、捨てる場所に困り、夜中バイクに便器を縛り付けて、丁度良さそうな木の下にそっと捨てたのだろうか。不法投棄をするにしても、もう少し場所を選ぶべきではないか。それとも、捨てたのではなく、あえてここに置いたのだろうか。神の化身とも見える一本の木の麓に、大切な便器を供えたのだろうか。
朝外へ出ると、気にすらしていなかった道脇の木の下に見たことない便器が転がっている。それはどんな気分なんだろう。朝の通勤でこの道を通る人は何日目ぐらいから、そこに便器があることを気にしなくなったのだろう。置かれた便器に指一本触れず、撤去もせず、あるがままに、自然のままにしておこう、という決断に至ったここの社会全体の度量の深さは、私の想像を遥かに飛び超え、異世界を見せてくれた。用を足すための便器が、用無しとなり、道に転がり、ずっとそのままになっている。しばらく便器を眺めていると、「ようこそインドへ」と思考のカオスを白紙に戻すように、どこからか甲高い鐘の音が鳴り響いた。

来た道を戻っていたつもりだったけど、少しして道を間違えたことに気がついた。しかし目の前にある塀の間から大量のバイクと人が見える。なんだろうと考えながら中へ入ると、寺だった。奥の本殿では音楽がきこえ、たくさんの人が群がっていた。ゆっくりと本殿の中へ入ると、録音かと思っていた音は生演奏だった。音質がなんとも言えないけど、全部ひっくるめたら最高のセッティング。祭壇の下で歌い手の女性が六人、タブラの青年、手拍子を打つ師匠っぽおっさん、あと数人が何かの楽器を演奏していた。祭壇の中心を囲むように長太い行列ができていて、花と霊水で礼拝を済ました人たちがところてんのように外へ出ていったかと思えば、次々に人が列に並んで行く。2周目の人とかいないよね?と途中疑ったぐらい人がたくさんいた。
お祈りを済ませた人たちに紛れながら演者の傍の空いたスペースに荷物を置き、腰を下ろした。空間を埋め尽くすのは演奏による音楽というより、音楽と祈り、瞑想、宗教、音を奏でる本来の目的がそこには充満していた。人に聞かせることをいちばんの目的にしていない音楽だった。実際一曲が終わっても、誰も拍手をしないし、演者に視線を向ける人もひとりもいない。皆、祭壇の中心にある仏の像一点を目掛け、胸の前�で手を合わせている。演者はなくてはならない仏具の一部かのように、寺院中に存在していた。宗教がこれほどまでに大衆の人々の”人生そのもの”になっている空間を初めて味わったような気がする。至極の美の空間だった。人も空間も音楽も全てが祈りに向かっていて、この地球上には悪人や敵なんて一人もいなくて、祈りが社会全体の意識の一部になった時、人類は一丸となり、世界は平和を築くことができるような気がした。
生まれながらの悪人なんて一人もいない。誰しもたまに、間違った言動をとってしまう不完全な存在。行動は否定しても、存在は決して否定しないで、あらゆる人を受け入れる度量を私たちはすでに持ち合わせているのではないか。たとえ道に便器を捨てる人がいても受け入れる。そしてそこに置かれた便器すらも受け入れる。問題を生み出すのはいつだって人が持つ概念だ。人が問題を作り、人が問題を解決する。そもそも問題にすらならなければ、解決する必要もない。インド人にはトイレットペーパーは必要ないから、そこにないのであって、お金がなくて補充されていないわけではない。あらゆる問題にまみれすぎて問題を起こさないことに神経を注ぐ小皿のような日本とは似ても似つかない、深い海溝のようなインド人の度量に、輝く哲学の光を見た帰り道。

用のない
便器が道に
落ちている
寺では人が
祈っています