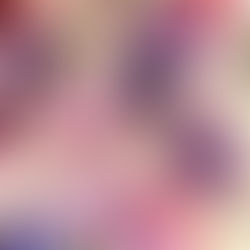車一台分ぐらいの狭い道幅の両脇に3畳ぐらいの小さな店が通り一面びっしりと並んでいる。野菜を並べる八百屋、バナナやココナッツを並べる果物屋、一台のミシンを店先に構える服の修理屋までいる。お菓子を買いに来た子供や、50キロはありそうな豆の袋を担ぎ、「通してー!」と何度も声を上げながら、枝のように茶色く細い足にビーサンを敷いて闊歩するおじさん。日曜日の昼過ぎ、市場の通りはもっとも賑わう時間だ。
混雑の奥へ進むと、生々しい生き物の匂いが風に運ばれ鼻を突いた。肉屋が近い。まあでも、生肉や生魚の匂いが人混みに紛れているのも悪くはない気分だった。臭いと言えば臭いけど、耐えられないほどではない。肉を買う時に、肉の匂いという生々しさがあることは、食生活のリアリティを映し出しているような気がした。毛をむしられ、内臓を取り除かれた鶏がショーケースに並べられている。鶏肉屋のバックヤードにはまだ動いている鶏が7、8羽入った檻が何段か積み重ねられていた。店主は口を動かし続けたまま、丸太の上でトントンと鶏肉をぶつぎりにして秤に乗せている。ここには冷蔵庫がない。その日その場で絞めた鶏を肉にして新鮮なものを提供しているから、冷蔵庫は必要ないようだ。絞めて、捌いて、整えて、売るまでがここでの肉屋の仕事。
この日は、魚とエビを買った。魚はその場で捌き、エビは殻を剥いてもらった。一つの通りに50店舗ほどが集結したクヌールのマーケット。それは企業テナントがひしめき合う大型スーパーとは対極にあって、小さな個人商売がいくつも集まり、その何倍もの数の人々の生活を支える、暮らしの拠点のような場所だった。人の熱気を感じながら買い物をすることはとてもわくわくした。出来上がるのを待っている間、魚の特徴や料理の仕方を店主に聞いたり、世間話をした後、「ありがとー!」と手を上げて、買い物を終える。
インドでの買い物は楽しい。どこの店もだいたい個人経営の小さな店だから、どんな買い物も必ず店の人と会話する。さらにインド人はよく喋るから、つられて私もよく喋る。当たり前のように人間味に溢れている買い物の熱量は、いつごろまで日本の日常にもあったのだろうか。便利で快適な近代化に埋もれてしまった大切な感覚が、クヌールの街にはまだたくさん残っている。もちろん周辺にはスーパーマーケットのようなものもあるけれど、きっと彼らにはこういう昔のままのスタイルの市場が絶対になくてはならないものなんだ。音源はデータになっても、レコードは錆びるどころか輝きを増すように、地元の市場での買い物は格別な気分だった。

古き良き買い物の風景の中に、ちゃっかり近代化をしている部分もある。決済は全てQRコードだった。お金というものが完全にデジタル化していた。どんなに小さなお店での、どんなに少額の買い物でも、全てオンラインでの決済が主流となっていた。理由を聞くと、コロナ禍の期間、お札が一番の感染経路だと判断したらしく、マスクをつけてスマホで支払いを済ませる新しいマナーが普及したそうだ。ちなみに、インド人はみんなタダで口座を開設できて、手数料なしでお金を支払うことができる。カード会社に払ったり、現金を引き出したりする時に手数料がないことも全国民に行き渡った理由の一つ。そもそも手数料なんかあったら、一円でも値切りたいという共通意識をもった大半の国民に普及する訳がないそうだ。
ちなみにインドの電話番号がないとシステムを利用できないため、海外SIMを入れた私のiPhoneでは利用できなかったため、私はほぼ現金とたまにカードを使っていた。
消費税に加えて決済手数料の両方を払わなきゃいけない日本はやっぱ変。そもそもゼーキンフィルターでみっちり濾されて溜まったお金を使う時にもう一度フィルターにかけなくてはいけないなんてひどすぎる。かといって預けたお金を引き出すのもお金を払わないといけない。そして払ったお金は一企業へと吸い込まれていく。勝手にとらないでほしい。沢が集まり川となり、川が集まり、大流をつくり、海へと帰り、雲になって雨になる。そうしてまた、山から沢ができていく。そんな風にお金が回ったらいいのにな。
地元民の間で物とお金が行き交うローカルエコノミーがしっかりと機能しているクヌールの町は、時代と逆走をしていたかと思えば、実は先端を行っているように見えた。井の中の蛙は、外を出てはじめて自分が蛙だと知るように、日本の外に出て初めて知れる日本がある。インドの田舎の市場が教えてくれた。