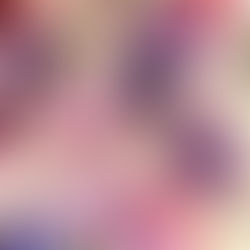グァバ、パッションフルーツ、マンゴー、グズベリー、コーヒー。茶の木の間に山鳥が運んだ種が芽を出して、大きな木になって、野生味あふれる実をつけている。食べごろになれば、鳥と仲良く取り放題だ。
インドの人口は14億人。多い!人口の半数以上は25歳以下で、この若い労働力がインドの経済成長の大きな原動力となっていて、しかも労働人口の約40%が農家である。インドは世界第二位の農地面積を持ち、米、小麦、綿花、茶なのどの主要な生産国となっていて、GDPの17%(約33兆円)を占めている。ちなみに日本の農業者比率は2%で、GDPの1%(8兆円ぐらい)。人がたくさんいれば、その分たくさん生産してたくさん消費もする。こうして数字を見比べると日本とインドは全く異なる発展のフェーズにいることが見て取れる。
もちろん経済が急速に発展しているとはいえども、例えばこの近辺の茶積みをする人たちの平均月収は12000円〜15000円ほどで、日本の平均月収の10分の1程度と非常に低い。しかし、ここで勘違いしてはいけないと思うのは、収入が多ければ豊かな生活で、収入が低ければ貧しい生�活になるというのは、単に経済的に裕福な生活をしている人から見た「貧しい」という意味でしかないということ。高所得=裕福・低所得=貧乏という方程式は、今の時代にはそぐわない。生きるということは、そんな単純な話ではない。
日本に限らず、経済的に豊かになった国では、時間とプロセスを短縮したり、精神をすり減らしたりしながら”まとも”な暮らしを維持せざるおえない人が多い。経済発展の行く末には、結局苦しい生活が待っていた。”発展”の意味とはなんだろうか。資本主義経済である以上、そのルールの特性から世界各国内に経済格差が生まれるのは当然のことだ。しかし、いざ茶摘みベテランのおばちゃんの清々しい微笑みを受け取った時、満員電車のおじさんの表情とは似ても似つかない、生命としてのそもそもの純粋さに私たち国と大きな格差があるような気がした。貯金がいくらとかじゃなくて、ただ生き生きとした人生を送りたい、土の上で生きたい、そう思った。
上京して3年、人混み、騒音、大気汚染、まずい水、スーツ、不便な要素がてんこ盛りの都会での生活に、全く未来を感じなくなってしまった。向き不向きがあって当たり前だけど、私の場合、田舎で地域との繋がりを大切にしながら、まずは美味しい水と空気と食��に囲まれ、地球の上で暮らしていくのに健全でオーガニックな生活の営みの方があっているみたい。だから、ここも初めて来た場所だけど、妙に落ち着く。自然に囲まれていたら世界中どこでも生きていけるような気がした。

話が脱線したが、農業の話に戻ろう。日本では農家のほぼ全てをJAがほぼほぼ一括管理しているけど、インドは必ずしも農業の全てが中央集権的ではなく、様々なビジネスモデルや地域自治組織が存在する。
例えば、クヌールという隣街にチェリーベリーというかわいらしい名前のスーパーマーケットがある。しかし、マルエーやオオゼキのようなただのスーパーマーケットではない。チェリーベリーは自社で農園を持っていて、そこで生産したものを直売するfarm to tableをコンセプトにしている複合型農業系企業だ。元製茶工場を改装したスーパーの2階はカフェとレストランになっていて、新鮮な野菜を使った地元の料理が楽しめる空間になっている。
石川の道の駅や直売所では、個々の農家が直接品出しを行い、売れ残ったものは各自回収するというスタイルだが、チェリーベリーでは自社で農地を保有し、農家を雇用している。つまり、年一回しか収穫できないなどといった生産リスクは農家個人ではなく、会社組織にある。しかも、インドでは農業に対する税金は免除されている。法人税も所得税も払わなくていいのだ。それならば個人が就農コストをかけずに農業に従事することができる。農家を直接雇用する、フードビジネスが地方にあると言うところがすごいと思った。日本では、農業法人しか農地を所有できないため、小規模の農家は参入しずらいし、そもそもリスクを背負いながら少ない休みで肉体労働をするというマイナスイメージばかりが先行し、職業人気ランキングのかなり下の方にいる。米がスーパーから消える前に、今こそ農業を優遇し、規制を緩和し、参入障壁を下げ、チェリーベリーのような企業を地方で増やしていくのがいいと思った。
クヌールはウチのそばで行ったら山代ぐらいの規模感で、決して都市ではない。そんな小さな街で、ローカルアグリビジネスが成立しているのを目の当たりにすると、浮き彫りになるのはインドの人口の多さだけでなく、地域社会にも多様な志向・価値観がちゃんと存在しているということだ。また、ニルギリ地区には有機農家を支援する民間組織があって、毎週ファーマーズマーケットを開催したり、マーケティングのサポートなどを行っている。政府機関の建物を利用し、土曜日の10時に開催されるマーケットにリシが連れて行ってくれた。5つか6つのブースがあり、どこも机いっぱいに野菜や果物が並んでいて、そ��の後には必ず農家がいた。農家が直接売りに来ているからファーマーズマーケットなんだと思った。お客さんは皆、農家におすすめの調理法を聞いたり、いつまで収穫できるかなど細かいことを聞いたりしながら、買い物そのものを楽しんでいた。

何より活気に溢れていた。朝の開店ちょっとすぎについたけど、すでにたくさんの人が集まっていた。その中に一際活発に動き回る一人の女性がいた。マーケットのオーガナイザーだ。リシの知り合いということもあって紹介してもらった。森で暮らす動物のように力強く輝く目をもった50代ぐらいの女性で、とにかくエネルギーに満ち溢れていた。「こっちにきなさい!はい、次はこっち!」と次々にブースに出店している農家を紹介してれた。オーガニックカルチャーを牽引するリーダーに相応しい、ついて行きたくなってしまう安心感と愛に溢れた強引さがとても気持ちのいい方だった。農作物も大地も体も全部オーガニックであることに信念を持ち、厳しい環境に置かれた小規模で少量多品目を作るサステナブルな農家たちをサポートする役割を担う、ニルギリのビックマザー。

ファーマーズマーケット。農家のためのマーケットであり、農家と消費者をつなぐ重要なパイプの役割を果たしてくれる。
卸業者に出荷して完結するのではなく、こだわりを持って作ったものだからこそ直接食べる人に色々なことを伝えながら、手渡すことができるのがファーマーズマーケットのいいところだ。人参一本、豆一粒、普通のスーパーで買えば値段しか気を留めないけど、農家から直接購入し、どんな人が作ったのかを少しでも垣間見ることができたならば、きっとその価値とおい��しさは何十倍にも広がり、農家の喜びとやる気もぐんと上がる。いいことしかない。

日本の田舎には仕事がない、とよく言われる。しかしそれは仕事がないのではなく、半歩先を見据えて新しい分野の仕事を作る感覚と情熱を持った人がいないという意味だ。本来仕事を作ることに場所は関係ないし、自信と人との繋がりさえもてれば、過疎地でもできないことはないのかもしれない。インドの地方でオーガニックムーブメントを巻き起こす農家たちの誇り高き眼差しに触れ、そう思った。